ウォーミングアップは、ケガの予防やパフォーマンスの最大化のために欠かせない準備です。
しかし、「何となくストレッチして軽く走るだけ…」になっていませんか?
実は、科学的に効果が認められているウォーミングアップのメニューが存在します。
今回は、初心者の指導者の方でもすぐに実践できる5ステップ構成のウォーミングアップメニューを、
信頼性のある論文をもとに、わかりやすく解説します。
チーム指導でも個人トレーニングでも使える内容なので、選手の準備をより確実に整えるための参考にしてみてください。
※下記時間・強度はあくまで目安であり、個々人の体力や競技レベルに合わせて調整してください。
Step 1: 全身の準備運動【General Activation】(3〜5分)
•目的: 体温・心拍数をゆるやかに上げ、全身をほぐす
•目安の運動強度: 「少し息が上がるけど、会話はできるくらい」
(目安:HRmax(最大心拍数)の50〜60%程度)
• 例:
・軽いジョギング、スキップ、軽めの縄跳び
・バイクやローイングマシン(低負荷・ゆっくりしたペース)
🧠 HRmax(最大心拍数)って?
最大心拍数(HRmax)は、運動時の心拍数の目安を決めるための基本となる値です。
以下の計算式でおおよその値を求めることができます:
👉 最大心拍数(HRmax) ≒ 220 − 年齢
たとえば、30歳の人なら…
→ 220 − 30 = 190拍/分(これがHRmaxの目安)
ウォーミングアップでは、この値の50〜60%(= 約95〜115拍/分)を目指して動くとよいでしょう。
📘 HRmaxやVO2maxについて、より詳しく知りたい方はこちらも参考に:

Step 2: 動的ストレッチとモビリティ【Dynamic Stretching & Mobility】(3〜5分)
•目的: 関節可動域の向上、筋肉の弾性を高める、動きのスムーズさを出す
• 例:
•レッグスイング(前後・左右)
•ウォーキングランジ+上半身の回旋
•“World’s Greatest Stretch”(ハムストリング・股関節・胸椎の動的ストレッチ)
•アームサークル、肩甲帯のモビリティドリル
•インチワーム+プッシュアップ(軽め)
🧠 さらに詳しく知りたい方へ
ダイナミックストレッチの「効果」「科学的な裏付け」「競技別の導入法」まで詳しく知りたい方は、以下の記事もぜひご覧ください👇

Step 3: 筋肉の活性化【Muscle Activation】(3〜5分)
•目的: 競技で主に使用する筋群を賦活し、安定性・連動性を高める
•例:
•ミニバンドを使ったサイドステップ、クラムシェル
•グルートブリッジ、ヒップスラスト(軽負荷)
•ウォールドリル(壁に手をついてマーチング動作など)
•スキャッププッシュアップ、バンドプルアパート(肩甲骨周囲)
•Y・T・Wエクササイズ(マットまたはベンチ上で)
📝 おすすめアイテム
ミニバンド:「パフォームベター」
✅ おすすめの理由(特徴)
・高い伸縮性と耐久性:全周約48cm・幅約5cmのバンドは、最大2.5倍まで伸びるため、あらゆる動きに対応しやすい設計です。
・耐久性に優れ、日常的な使用や強度の高いセッションにも安心して使えます。
・クライアントの多様な体格や目的にも柔軟に対応できる点が、多くの現場で評価されています。
特にチーム指導やグループセッションでは、強度別に複数本揃えておくと効果的です。
インナーマッスル用チューブ:「Jバンド」
✅ おすすめの理由(特徴)
手首に固定できる設計により、前腕に力が入りにくく、肩甲骨まわりやインナーマッスルにしっかり刺激を入れやすいのが特長です。
野球やバレー、テニスなど肩の安定性が重要な競技に最適です。
Step 4: 神経と反応の刺激【Neural & Reaction Activation】(2〜4分)
•目的: 神経系を刺激し、反応速度・敏捷性を高める
• 例:
•ラダーやマーカーを使ったクイックフットワーク → 短いダッシュ
•ラインホップや低強度のバウンディング(プライオメトリック要素)
•パートナーとミラードリル、リアクションボールキャッチなど
•Aスキップ、Bスキップなどのランドリル
当ブログでは【GAVIC(ガビック)製】をおすすめしていますが、他メーカーのものでも問題ありません。
選ぶ際は「サイズ(直径)」を基準に、練習環境や対象年齢に合わせて選ぶと良いでしょう。

Step 5: 視覚と競技動作の連携【Dynamic Vision & Sport-Specific】(3〜5分)
•目的: 視覚的なトラッキング能力を高め、競技特異的動作へスムーズにつなげる
• スポーツ別例:
•野球: ボールトラッキング(トス→キャッチ)、軽いスローイング、肩周りのモビリティ
•サッカー: ラダーフットワーク→パス交換、素早い方向転換
•バスケット: ボールキャッチ&パス、サイドシャッフル、ディフェンススライド
•バレーボール: アプローチステップ、壁を使ったブロック動作、簡易レシーブ反応
•テニス: シャドーストローク、スプリットステップドリル、リアクションボールキャッチ
👀 視覚トレーニングをもっと深く知りたい方へ
視覚の鋭さやトラッキング能力は、パフォーマンスに直結する重要な要素です。
特にボール競技では、「目で捉える力」を鍛えることで反応速度や判断力が向上します。


実践上のアドバイス
1. 時間配分の柔軟性
チーム競技では、人数や器具の使用状況によってプログラムの進行が変わることがあります。余裕をもって12-20分を想定し、必要に応じて一部種目のセット数や回数を調節してください。
2. 静的ストレッチの扱い
一般に「パフォーマンスを下げないために、長時間の静的ストレッチは避ける」が推奨されています。しかし、可動域改善を特に要する部位(例:股関節が硬い、肩甲骨まわりが硬いなど)がある場合は、短時間の静的ストレッチを軽く挟むことで怪我予防につながる場合もあります。その際はウォーミングアップの最初か中盤に留め、最後は必ず動きのあるストレッチやアクティブドリルで終わることをおすすめします。
3. 個別化・怪我リスク管理
選手の年齢、コンディション、既往歴(膝や腰の痛みなど)に応じて、特定のドリルを除外したり負荷を減らすなど調整が必要です。特にプライオメトリック(弾む動き)系は関節への負担も大きいので、初心者やリハビリ中の方には強度を下げたり回数を少なくしてください。
4. メンタル面の準備
大会前や練習前で緊張が高い場合、ステップ1~2の段階から意識的に呼吸を整える・イメージトレーニングを並行するなど、ルーティン化したメンタル準備を取り入れるのも効果的です。
参考文献
•Bishop, D. (2003). Warm up I: Potential mechanisms and the effects of passive warm up on exercise performance. Sports Medicine, 33(6), 439-454.
•Behm, D. G., & Chaouachi, A. (2011). A review of the acute effects of static and dynamic stretching on performance. European Journal of Applied Physiology, 111(11), 2633-2651.
•Jeffreys, I. (2007). A Task-Based Approach to Developing Context-Specific Agility. Strength & Conditioning Journal, 29(5), 10–14.
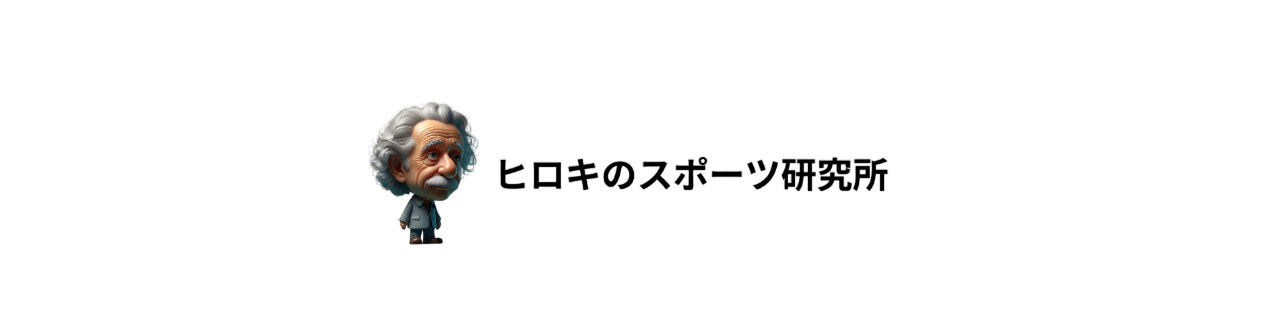



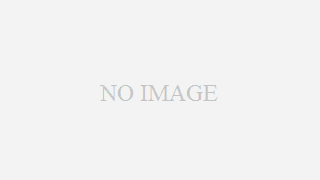







コメント