「エコロジカルアプローチって何?」
「環境が動きを決めるってどういうこと?」
そんな疑問を持つ指導者・選手の方に向けて、今回は今注目されている“感覚を引き出す指導法”=エコロジカルアプローチを、超わかりやすく解説します。
たとえば、
•タイミングがいつもズレる
•少し状況が変わるだけでミスが増える
そんな選手に共通するのは、「視覚だけに頼ったプレー」になっているという点です。
本記事では、「見る」だけでなく“感じて動く”感覚的なプレーを育てるための方法を、スポーツ科学の観点から紐解いていきます。
紹介する理論は以下の通りです:
•Gibsonのエコロジカル理論(アフォーダンス)
•Shams & Seitzの多感覚統合(マルチセンサリーラーニング)
•Schmidtのスキーマ理論(汎用性あるスキル形成)
これらの理論はすべて、「実戦に強いスキルを育てるにはどうすればいいか?」という問いに対して、非常に有効なヒントを与えてくれます。
指導者はもちろん、選手自身が「感覚的にうまくなりたい」と思っている場合にも役立つ内容です。
ぜひ最後までご覧ください!


🧠 Schmidtの「スキーマ理論」とは?
運動スキルは“決まった型”じゃなく、“ルール”として覚えるもの!
✅ ざっくり言うと…
「同じ動きを何度もやる」よりも、
「いろんな状況で動きを経験する」ことで、
動きを作る“ルール(=スキーマ)”が身につくという考え方です。
✅ もう少し詳しく
Schmidt(1975)は、「運動は記憶された“ルール”によって再構成される」と考えました。
このルールを スキーマ(schema) と呼びます。
たとえば、バレーボールのスパイクを例にすると…
【❌旧来の考え方】
スパイクの動作は「この形、このタイミング」と一つの型で記憶される
【✅スキーマ理論の考え方】
スパイクの動作は「ジャンプの高さやトスの速さに応じて毎回自分で調整する」
→ つまり、「動作を作るルール」を覚えている!
✅ スキーマ理論が説明する4つの情報
スキルを使うたびに、脳内では次の4つの情報が記録・整理されます:
|
番号 |
情報の内容 |
例(スパイクで考えると…) |
|---|---|---|
|
① |
初期条件(環境や体の状態) |
トスの高さ、助走のスピードなど |
|
② |
動作のパラメータ |
ジャンプのタイミング、スイングの速さ |
|
③ |
結果 |
ボールの飛び方、スピード |
|
④ |
感覚情報(フィードバック) |
うまく当たった?手ごたえは? |
この4つを何度も経験することで、
「こういう状況ならこう動く」というルール=スキーマが構築されていくのです。
✅ 重要ポイント:「スキーマ」を作るにはバリエーションが必要!
•同じ状況・同じ動作だけでは、スキーマは育ちません。
• 少しずつ違う状況(トスの高さ・風船や重いボールなど)で繰り返すことで、「応用力のある運動スキル」が身につきます。
🎯 スキーマ理論が実際の指導に役立つ場面
|
シーン |
旧来の教え方 |
スキーマ理論に基づく教え方 |
|---|---|---|
|
スパイク練習 |
毎回同じトスで打たせる |
トスの高さ・タイミングを変えて練習する |
|
パス練習 |
同じ距離・同じスピード |
強弱・角度・種類を変える |
|
子ども指導 |
正しいフォームを繰り返す |
いろんな動きの中で“自然に”身につけさせる |
✅ まとめ:スキーマ理論のポイント
•「型を覚える」のではなく、「動きを作るルール(スキーマ)」を育てる
•スキーマを形成するには、いろんな状況での練習=変動練習が必要
•実戦での対応力やミスへの順応性が高まる
🔁 おまけ:シンプルなたとえ話
📌 「料理のレシピ」よりも、「料理の作り方のコツ」を覚える感じ!
•レシピだけだと、材料や分量が変わったときに困る
•でも「コツ(スキーマ)」があれば、多少変わっても上手に作れる
スパイクも同じです!
「動きそのもの」より「どう動きを調整するか」が大事だというのがスキーマ理論です。
🧠 Shea & Morganの「変動練習」理論とは?
“同じことの繰り返し”より、“いろんなやり方”の方が、スキルはよく育つ!
✅ ざっくり言うと…
同じ練習ばかりしていると、上達した気になるけど実は応用がきかない選手になりがち。
ちょっと難しい・毎回違う・混ざっている練習こそが、真のスキルを育てる!
これが、Shea & Morganの「コンテクスチュアル・インターフェアレンス理論(文脈干渉効果)」に基づいた変動練習の考え方です。
🔍 実験の概要(1979年)
Shea & Morganは、ある運動課題を学習する被験者を以下の2つのグループに分けました:
|
グループ |
練習内容 |
|---|---|
|
① 固定練習グループ |
1つの動作を繰り返し反復(Block Practice) |
|
② 変動練習グループ |
複数の動作をランダムに練習(Random Practice) |
🧪 結果はどうなった?
•練習直後は「固定練習」の方がうまくできた(すぐ上達したように見える)
•でも数日後のテスト(保持・転移テスト)では、
👉 変動練習グループの方が圧倒的に良い成績を残した!
🟢 つまり:
練習中にあえて混乱がある方が、長期的に見て“本物のスキル”になるということです。
📌 なぜ「変動」がスキルを強くするのか?
•毎回同じ動作だと、「自動的に繰り返すだけ」で済んでしまう
•でも毎回条件が違うと、「毎回“考えて・判断して・調整”しないといけない」
🔁 その積み重ねが、
→ 運動スキルの再構成力・応用力・汎化力を高める!
🏐 バレーボールでの応用例
|
練習法 |
内容 |
得られる効果 |
|---|---|---|
|
固定練習 |
毎回同じ高さ・同じ角度のトスでスパイク |
タイミングや形を覚えるが、実戦でズレに弱い |
|
変動練習 |
高さ・速度・位置の違うトスを交えて打つ |
タイミング調整・判断力・対応力が育つ |
✅ 実戦で起こる“イレギュラー”に対応できる選手になるには、変動こそが最良の練習です。
💡 「うまくできない練習」こそが、実は一番効果的
選手が「難しい」「毎回違う」「ミスしやすい」と感じるような練習でも、それが 変動練習の理想的な状態 です。
❌ 上手くできて満足して終わる練習より
✅ 考えながら、調整しながら行う練習の方が、長期的な上達につながる!
✅ まとめ:変動練習のポイント(Shea & Morgan 1979)
•「毎回違う課題」「少し混乱を伴う練習」の方が、記憶や応用力の面で効果が高い
•練習中にうまくできるかより、「あとで活かせる動きを作れるか」が大切
•実戦に近づけるには、「変化」「変動」「予測不能な環境」を加えた練習が必要!
🔁 シンプルなたとえ話
📌 「毎回同じ鍵を開ける練習」より、「毎回違う鍵を開ける練習」の方が、本物の鍵師になれる!
🧠 Gibsonの「知覚理論(エコロジカルアプローチ)」とは?
“見る”とは、単に目で捉えることじゃない。環境の中で“意味”を感じ取ること!
✅ ざっくり言うと…
人は、目に入った情報をただ処理しているのではなく、
「その場の環境」から“行動のヒント”を直接キャッチしているという考え方です。
👓 視覚は「環境の中で使う力」
▶︎ 旧来の考え方(情報処理モデル)
•見る → 脳で解釈する → 動く
(例:ボールの位置や速度を測定 → 脳で計算 → 手を動かす)
▶︎ Gibsonの考え方(エコロジカル理論)
•見た瞬間に「どう動くか」が“直接的にわかる”
(例:ボールの落下を見て、“ここでジャンプすれば打てる”と自然に判断)
🔑 Gibson理論のキーワード:「アフォーダンス(affordance)」
アフォーダンスとは、「環境が人に与える行動のきっかけ」のこと。
🟡 たとえば:
•ドアノブを見ると「回せそう」と感じる
•ジャンプ台を見ると「跳べそう」と感じる
•高いトスを見ると「今なら打てそう」と感じる
この「◯◯できそう」という直感的な“感じ”こそが、Gibsonが言う知覚の本質です。
📌 スポーツに当てはめると?
•ボールを「見る」だけでは足りない
→ “どう動くか”を即座に判断する能力が求められる
•つまり、選手にとって重要なのは:
❌ 情報を測定する力
✅ 環境に反応して動きを“見つける”力
🏐 バレーボールでの例
|
状況 |
旧来の考え方 |
Gibsonの理論的な見方 |
|---|---|---|
|
スパイク練習 |
トスを正確に目で追い、ジャンプのタイミングを「計算」する |
トスの高さ・落下スピードを見て「打てそう」と感じた瞬間に動く |
|
試合中の反応 |
予測や経験で対応 |
視覚・空間・動作の統合的な直感反応が鍵 |
✅ Gibson理論を活かした指導のヒント
🔁 単純な繰り返しより「環境の変化」を!
•同じ場所から同じ高さのトスばかり → ❌
•毎回少しずつ違うトス(スピード・高さ・角度)→ ✅
🟡 ボールの種類を変えるのも効果的
•重い・軽い・大きい・不規則なボールを使うことで、選手のアフォーダンス感覚が鍛えられる!
✅ まとめ:Gibsonの知覚理論のポイント
•人は環境から「直接的に意味のある情報」を受け取っている(=アフォーダンス)
•視覚は「見るため」ではなく、「動きを導くため」にある
• スポーツ指導では、選手が自分で“気づいて動ける”状況をつくることが大切
•繰り返しではなく、「変化」の中で判断力と感覚が磨かれる
🔁 シンプルなたとえ話
📌 「視覚」はカメラではなく、ナビゲーション!
•カメラはただ映すだけ
•でもGibson理論では、視覚は「どこに向かえばいいか」「どう動けばいいか」を教えてくれるナビのようなもの
🧠 Newellの「制約主導アプローチ」とは?
“選手の動き”は、体・環境・目的の影響を受けて自然に変化する!
✅ ざっくり言うと…
「このフォームが正解だよ」と教えるのではなく、
選手の体や環境、やるべきこと(課題)を変えることで、自然と動きが育っていくという考え方です。
🏃♂️ 「正しい動き」は1つじゃない
Newell(1986)は、運動学習を「制約(Constraints)」という視点で説明しました。
動きは、次の3つの制約の影響を受けて生まれると考えられています。
🔺 3つの制約(Constraints)
|
種類 |
内容 |
例(バレーボールの場合) |
|---|---|---|
|
① 個体(個人)の制約 |
身体的・心理的特徴(身長・柔軟性・経験など) |
背が高い選手は助走を短くしても打点が高い |
|
② 環境の制約 |
気温、道具、床、スペースなど |
体育館と砂浜では動きが変わる/ボールの種類が変わる |
|
③ 課題の制約 |
ルール・目的・使用する技術など |
「ブロックを避けて打つ」など状況ごとの目的の違い |
🟢 この3つが組み合わさることで、選手の“その場に合った動き”が自然と生まれるというのがNewellの考えです。
🔄 フォームを教えるより、環境を工夫する
よくある指導:
「ひじをここまで上げて」「この角度で打って」→ ❌
制約主導アプローチの考え方:
「違う高さのボールを出してみよう」「小さいコートでやってみよう」→ ✅
→ 選手自身が“どうすればうまくできるか”を探し、動きを学んでいく
🏐 バレーボールでの活用例
|
工夫した“制約” |
目的・効果 |
|---|---|
|
風船を使ってスパイク練習(環境の制約) |
長く滞空するためタイミングを待つ力がつく |
|
小さなバレーボールを使う(課題+環境の制約) |
視覚依存を減らし、感覚で当てる力がつく |
|
利き手禁止ルール(課題の制約) |
身体全体を使ったコーディネーションが育つ |
|
足場を不安定にする(環境の制約) |
下半身の安定性と動きの調整力を引き出す |
✅ この理論を取り入れるとどうなる?
✅ コーチが「教え込む」のではなく、選手が「自分で気づいて学ぶ」指導になる
✅ 環境や課題を工夫することで、“実戦に強い動き”が自然に育つ
✅ フォームにとらわれず、それぞれの選手に合った動きが引き出される
🧭 シンプルなたとえ話
📌 「道順を教える」より、「地図を渡して自分でたどり着いてもらう」指導法
•細かく指示されて動くより、
•環境の中で「こうしたらうまくいく」を自分で発見する方が、応用力も定着力も高まる
✅ まとめ:制約主導アプローチのポイント
•運動は「選手の身体」「環境」「課題」の3つの制約が影響しあって自然に生まれる
•正しいフォームを教えるよりも、「環境やルールを変えることで動きが引き出される」指導が有効
•現場では、「ボール・コート・ルール」を変えてみることで、臨機応変な選手が育つ
🧠 Chowらの「非線形ペダゴジー」とは?
“正解のフォーム”を教えるのではなく、“自分で解決策を見つけられる選手”を育てる指導法!
✅ ざっくり言うと…
「この動きが正解だから、こうしてね」と教えるより、
「いろんな状況を体験させて、自分で動きを見つけさせる」方が、スキルはしっかり定着する。
これが非線形ペダゴジー(Nonlinear Pedagogy)の考え方です。
「正解を教える直線的な学び方(Linear)」ではなく、
“ゆらぎ”や“試行錯誤”の中でスキルを育てていく学び方を大切にしています。
📚 背景にある理論は「制約主導アプローチ」
この考え方は、Newellの「制約主導アプローチ(Constraints-led Approach)」に基づいています。
つまり、運動は以下の3つの制約の相互作用で成り立つという前提:
|
制約の種類 |
内容 |
バレーボールの例 |
|---|---|---|
|
個体の制約 |
身体・経験・感覚 |
身長が高い、ジャンプ力がある |
|
環境の制約 |
道具・場所・照明 |
体育館/砂浜、風船/公式球 |
|
課題の制約 |
ルール・目標 |
「速攻でスパイク」「ブロックを避ける」など |
この制約を意図的に操作することで、選手自身に気づかせる指導が、非線形ペダゴジーです。
🔁 なぜ「非線形」なのか?
❌ 線形(Linear)な学び:
•「段階的に」「正解を一つずつ」教えていく
•教わったとおりにしかできない選手になりやすい
✅ 非線形(Nonlinear)な学び:
•最初から完璧な動きは求めない
•環境・課題を変化させながら、“試行錯誤”を通じて動きを育てる
•結果として、実戦で応用できる“しなやかなスキル”が身につく
🏐 バレーボールでの実践例
|
工夫した指導 |
意図 |
得られる力 |
|---|---|---|
|
風船やビーチボールでスパイク |
ボールの落下が遅い → タイミング調整 |
リズム・集中力・判断力 |
|
コートサイズを半分に |
距離が短くなる → スイングの調整 |
空間認識・スピード適応 |
|
片手・逆手でのプレー |
課題を変える → 工夫せざるを得ない |
創造力・身体操作感覚 |
🟢 ポイントは、「動きを言葉で教える」のではなく、
“環境から学ばせる”仕掛けをコーチがつくること。
✅ この理論を取り入れるとどうなる?
✅ ひとつの“理想のフォーム”に縛られない
✅ 自分で「うまくいくやり方」を探しながら身につける
✅ 試合中の予測不能な状況にも強くなる
✅ 主体的に考える“学び方がうまい選手”になる!
🔁 シンプルなたとえ話
📌 「九九を丸暗記する」のではなく、「計算の仕組みを理解する」学び方
非線形ペダゴジーは、選手が「なぜ・どうすればうまくいくか」を体験を通して学ぶことに重点を置きます。
✅ まとめ:非線形ペダゴジーのポイント(Chowら 2016)
•正解を教えるより、「発見させる」指導
•環境や課題の操作によって、自然に動きが引き出される
•応用力・適応力・創造性を高める
•主体性ある学びをサポートするための“環境デザイン”がコーチの仕事
🧠 Shams & Seitzの「多感覚統合」理論とは?
見る・聞く・感じるを組み合わせることで、学びの精度は劇的に上がる!
✅ ざっくり言うと…
「見る」だけの練習より、
「見て・感じて・聞いて」動く練習の方が、
脳に深く定着しやすく、応用力も高くなる!
これが、Shams & Seitz(2008)が示した多感覚統合(Multisensory Integration)による学習効果の本質です。
🧬 脳は、五感を“まとめて処理”する
私たちは日常的に、
•目で見る(視覚)
•体で感じる(体性感覚・触覚)
•音を聞く(聴覚)
•動いて覚える(運動感覚=プロプリオセプション)
など、複数の感覚を同時に使って判断・行動しています。
Shams & Seitzは、これらを組み合わせた方が、学習や運動スキルがより早く・強く定着することを実験で示しました。
🧪 研究の背景とポイント
Shams & Seitz(2008)のレビューでは、次のようなことがまとめられています:
|
内容 |
説明 |
|---|---|
|
単一感覚よりも複数感覚のほうが、脳の学習システムが活性化される |
脳の「感覚野」だけでなく「統合野」も同時に動くため |
|
多感覚刺激を与えると、注意力・記憶力・反応速度が向上 |
学習のスピードと保持力が上がる |
|
幼少期から多感覚を活用して学ぶことで、柔軟な運動スキルが形成されやすい |
大人にも有効、特に運動再学習に強い効果 |
🏐 バレーボールでの実践例
|
感覚 |
具体的な刺激 |
練習の工夫例 |
|---|---|---|
|
視覚 |
ボールの軌道・相手の動き |
変化球のスパイクや視野の制限付き練習 |
|
聴覚 |
スパイク音、指導の声 |
声を使ってタイミングを合わせる「声出し連動練習」 |
|
体性感覚 |
空中での体の位置・手ごたえ |
ボールの種類を変えて、感触で判断させる |
|
運動感覚 |
スイング中の力の入れ方 |
片腕スパイク、目を閉じたまま動作練習 など |
🟢 重要なのは:
「1つの感覚に頼らせすぎない」こと。
→ 特に視覚ばかり使っている選手は、他の感覚を鍛えることでプレーの安定感が上がります。
✅ この理論を取り入れるとどうなる?
✅ ボールのスピードや位置が多少ズレても、“身体の感覚”で対応できるようになる
✅ 脳がより多くの情報を使って学習するため、スキルがより深く定着する
✅ 「視覚に頼らないプレー」=予測・判断が早い選手が育つ
🔁 シンプルなたとえ話
📌 「地図を見ながら歩く」のと「音声ナビも使う」のでは、どちらが迷いにくい?
→ 視覚だけでなく、複数の感覚を使った方が正確に・速く目的地にたどり着ける。
スポーツもまったく同じです!
✅ まとめ:多感覚統合のポイント(Shams & Seitz 2008)
•感覚はバラバラに働いているのではなく、同時に連携して“統合的に”働いている
• 視覚だけの練習では不十分。聴覚・触覚・体の内側の感覚も鍛えるべき
•複数の感覚を同時に使うと、学習効率が大きく向上
•バレーボールなどの動的スポーツでは、多感覚練習=実戦力を育てるカギ
🧠 【視覚だけじゃ足りない!】Gibsonのエコロジカル理論 × Shamsの多感覚統合で“プレーの本質”をつかむ指導へ
✅ 結論:視覚に頼りすぎた指導は限界がある。
選手の“感覚”を育てるには、環境と多感覚の活用がカギ!
🔍 Gibsonの「エコロジカル理論」とは?
▶︎ 見る=意味を“直接”感じ取る力
• Gibson(1979)は、人は環境の中から“行動のヒント”を直接的に拾っていると提唱。
•「見て→考えて→動く」ではなく、
→「見た瞬間に“どう動けるか”がわかる」=アフォーダンス(affordance)という考え方が軸。
📌 例:
•トスを見る →「今ならスパイク打てる」と直感的に感じる
•ボールの落ち方を見る →「ここにいれば拾えそう」と体が反応する
これは脳内の計算ではなく、“環境との相互作用”による知覚なんです。
🔍 Shams & Seitzの「多感覚統合」とは?
▶︎ 脳は「見る+感じる+聞く」を同時に使っている
• Shams & Seitz(2008)は、視覚だけでなく、聴覚・体性感覚などの“複数の感覚”を同時に使うことで、学習が深く・早くなると報告。
• これが「多感覚統合(Multisensory Integration)」という考え方。
📌 例:
•音を聞いてタイミングを取る
•空中での手ごたえで「当たりの強さ」を感じる
•見えない状況(目を閉じて)でもスパイク動作を再現できる選手は、感覚統合が発達している証拠!
🔁 2つの理論をつなげるとどうなる?
|
役割 |
Gibsonの理論 |
Shamsの理論 |
|---|---|---|
|
知覚の仕組み |
環境から“意味”を直接感じ取る(アフォーダンス) |
複数の感覚が統合されることで、反応が洗練される |
|
動きへの影響 |
「どのように動けるか」がわかる |
「どのくらい・どのタイミングで動くか」が正確になる |
|
トレーニングの方向性 |
環境に“意味”を持たせる練習 |
感覚を引き出す多様な刺激を与える練習 |
🟢 共通するのは、「動きを言葉で教えすぎない」「環境や感覚で気づかせる」という指導方針。
🏐 実践例:この2つの理論を活かしたバレーボール練習
|
練習の工夫 |
意図 |
引き出される力 |
|---|---|---|
|
ビーチボールでスパイク |
滞空時間が長く、タイミング調整が必要 |
アフォーダンス感覚(Gibson) |
|
目を閉じたままトスキャッチ |
視覚以外の感覚に集中 |
多感覚統合(Shams) |
|
照明を落としてトス練習 |
視覚情報を制限し、体性感覚に頼らせる |
感覚の幅を広げる(両理論) |
|
音声合図でスイング |
タイミングを聴覚から取らせる |
感覚統合力と反応精度 |
✅ この2つの理論を取り入れるとどうなる?
✅ 「見て動く」ではなく、「感じて動く」選手になる
✅ 試合中の不安定な状況にも強くなる(=臨機応変さ)
✅ 練習で“自分の感覚”を育てることができる
✅ 一瞬の判断や動作の質が、明らかに変わってくる!
🔁 シンプルなたとえ話
📌 目で見ただけじゃ、川を飛び越えられるかわからない。
→ 足場の感触、風の強さ、身体の準備、全部が“動けるか”の判断材料になる。
スポーツも同じ。
見える情報だけじゃなく、身体で“感じ取る力”があってこそ、強い選手になる!
✅ まとめ:Gibson × Shamsで導く感覚トレーニング
•Gibson理論:「環境から直接“意味”を読み取る力=アフォーダンス」を育てる
•Shams理論:「複数の感覚を統合して、精度の高い動作に仕上げる」
•共通する指導方針:「感覚を引き出す練習環境をつくる」「言葉より体験」
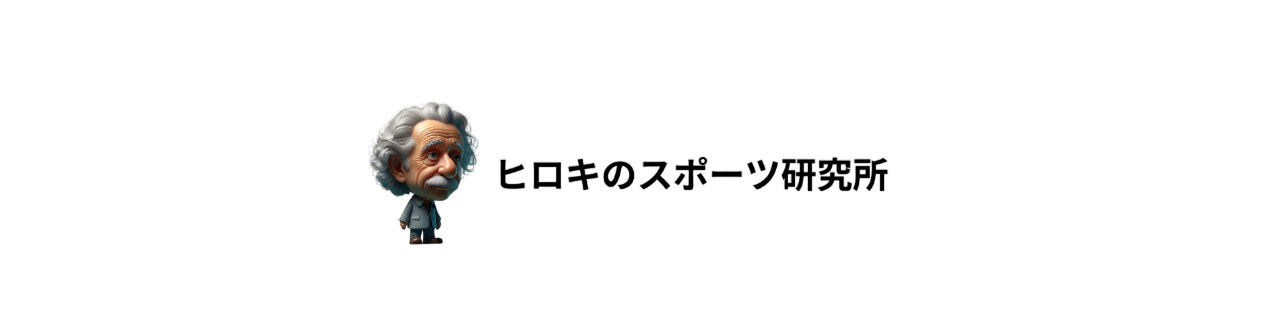



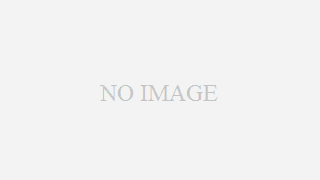



コメント