動体視力は「才能」ではなく、鍛えることができる力です。
打球への反応、パスの読み、相手の動きへの反応——
一瞬の判断が勝敗を左右する現代スポーツでは、「見る力=視覚スキル」が、技術や筋力と並ぶ“第3の能力”として注目されています。
特に重要なのが、動いている対象を正確に視認し続ける “動体視力” 。
この動体視力は、正しい方法でトレーニングすることで確実に向上させることが、近年の研究でも明らかになっています。
この記事では、
- 動体視力を鍛える効果的な方法
- 競技別・目的別の視覚トレーニングメニュー
- 科学的根拠に基づいた最新の研究知見
をわかりやすくまとめました。
「反応が遅い」「視野が狭い」「勘が悪い」と言われてきた選手も、“見る力”のトレーニングで大きく変わる可能性があります。
スポーツ現場に視覚トレーニングを導入したい指導者やアスリートの方は、ぜひ最後までチェックしてください!

野球選手のためのと書いてはいますが、どなたにでもどんなスポーツでも当てはまることを書いています。

【どうアスリートにアプローチすべきか?】
視覚トレーニングを選手に導入・継続させるためには、以下のような伝え方・考え方が効果的です。
①「視覚は脳の一部」と伝える
目は単なるカメラではありません。
見た情報を「判断」し「動作」につなげているのは脳です。
つまり、視覚トレーニングは視神経〜脳〜筋肉までの“判断と反応の連携”を鍛える脳トレでもあります。
視覚トレーニングは“眼の筋トレ”じゃなくて、“脳とカラダの連携”を速くするトレーニングです。
② 技術・フィジカルと同じく“伸びる能力”だと伝える
視覚系スキル(動体視力・周辺視野・反応力など)は、遺伝や才能ではなく「鍛えられるスキル」です。
一流選手が無意識で行っている「見る・判断する・動く」は、反復で習得できます。
視覚は筋トレと同じで、“反復するほど速くなる”
③ なぜ必要か?を競技別に伝える
抽象的な説明だけでは選手の納得感を得にくいので、その競技特有の“視る力”の重要性を絡めて説明すると効果的です。
例
- 野球 → 「動体視力で変化球の見極め精度が上がる」
- サッカー → 「スキャンの速さがパス判断につながる」
- バレー → 「スパイクの予測は“視る前に予測する力”」
このように「なぜ必要か?」「どう変わるか?」「どう伝えるか?」を整理することで、現場での導入がグッとスムーズになります。
競技別DVTプログラム例
以下は、競技特性に合わせたダイナミックビジョントレーニングの実践例です。
現場で簡単に導入できるよう、器具なし/器具ありの両方を交えています。

目的別おすすめDVTトレーニング一覧
|
目的 |
トレーニング例 |
主な競技 |
用具・器具 |
根拠論文・参考 |
|---|---|---|---|---|
|
動体視力向上 |
トラッキングトス(動くボールの軌道を追う) |
野球 卓球 |
テニスボール、卓球ボールなど |
Poltavski et al. (2020) |
|
スムーズパスート練習(眼球で動く対象を追跡) |
卓球 テニス バドミントン |
視覚ターゲット、ペンライト |
Poltavski et al. (2020) |
|
|
Okkuloライトトレーニング(照度を調整した環境で動く対象を捉える) |
サッカー ラグビー |
Okkulo特殊照明システム |
Rodrigues et al. (2024) |
|
|
反応・視野拡張 |
ストロボドリブル(視覚制限下でドリブル) |
バスケット サッカー |
ストロボグラス |
Wilkins & Appelbaum (2019) |
|
周辺視野反応ドリル(周辺のターゲットに素早く反応) |
バスケット ラグビー |
Fitlightなどの光刺激器具 |
Appelbaum et al. (2016) |
|
|
デュアルタスクパス(視野拡張と認知負荷の同時刺激) |
バスケット サッカー ハンドボール |
複数色のボール、マーカー |
Appelbaum et al. (2016) |
|
|
反応速度改善 |
フラッシュレシーブ(瞬間的な光に反応) |
バレー 卓球 |
Fitlightなどの光刺激器具 |
Li et al. (2024) |
|
ストロボサーブレシーブ(ストロボ眼鏡使用で予測反応力強化) |
バレー |
ストロボグラス |
Scientific Reports (2024) |
|
|
フラッシュライトタッチ(光るターゲットに触れる) |
野球 格闘技 ハンドボール |
Fitlight |
Appelbaum et al. (2016) |
|
|
視覚反応速度短縮 |
スキャンビジョン(周囲確認の速度を高める) |
サッカー ラグビー |
特に用具なし、視覚認知トレーニング |
Jordet (2005, 2013) |
|
ストロボキャッチ(ストロボ使用で反応速度を高める) |
ラグビー 野球 アメフト |
ストロボグラス、ボール |
Wu et al. (2024) |
|
|
Okkuloライトトレーニング(暗所での視覚処理を速くする) |
サッカー フットサル |
Okkulo特殊照明システム |
Rodrigues et al. (2024) |
トレーニングの選び方(ポイント)
- 動体視力向上
- 素早く動く対象を捉える能力向上を目指します。
- 速球系スポーツに有効。
- 反応・視野拡張
- 周辺視野の広さや認知負荷に対応する力を高めます。
- チームスポーツ全般に効果的。
- 反応速度改善
- 視覚刺激に瞬時に反応するスピードの改善を目的とします。
- 反射や俊敏性が重要な競技に最適。
- 視覚反応速度短縮
- 視覚情報を脳内で処理し、運動指令に変換するまでの時間を短縮します。
- スピード系や判断力が求められる競技向き。
目的に合ったトレーニングを導入し、効率よく視覚機能を鍛えましょう。
動体視力向上トレーニング
① トラッキングトス(Tracking Toss)
概要
動いているボールの軌道を最後までしっかりと目で追い続けるトレーニングです。
目的
動体視力、つまり動いているものを正確に視認し続ける能力の向上を図ります。
- パートナーやトレーナーが、前方や横方向からランダムにボールを投げます。
- 選手は身体を動かさず、頭と目だけでボールの動きを追います。
- ボールが手元に来たらキャッチ(または打ち返す)し、正しく追跡できたかを確認します。
- 慣れてきたら、ボールのスピードや方向をランダムに変えるとより効果的です。
② スムーズパスート練習(Smooth Pursuit Training)
概要
眼球をスムーズに動かし、動く物体をなめらかに追跡する練習です。
目的
視線の移動が途切れないようにし、動いている対象物を滑らかに追う能力を高めます。
- 選手の前方で、指や専用のターゲットを左右または上下にゆっくり移動させます。
- 選手は頭を動かさず、目だけでターゲットを追います。
- 眼球が飛び跳ねるような動き(ジャンプ)がないかを確認し、できる限りスムーズに追えるよう練習します。
- 難易度を高めるために、ターゲットの移動速度を徐々に速くしたり、予測しにくい動きを取り入れたりします。


③ Okkuloライトトレーニング(Okkulo Light Training)
概要
特殊な照明(暗くした環境)でトレーニングを行い、通常よりも目が対象物を捉えることが難しい状況を意図的に作り出します。
目的
視覚が制限された環境下でのトレーニングによって、動体視力と視覚処理速度を同時に鍛えます。
- 薄暗い室内(専用のOkkuloライト環境)を準備します。
- ボールやターゲットをランダムな方向に移動させ、それを選手が正確に視認し、反応します。
- 選手は徐々に慣れることで、視覚情報を効率よく処理し、反応時間を短縮できるようになります。
- 明るい環境に戻ったときに、視覚的な反応速度や精度が著しく向上する効果が得られます。
Okkuloシステムはアメリカやヨーロッパでは一定の認知度がありますが、日本ではまだほとんど導入例がなく、あくまでも紹介レベルとしての位置づけです。

反応・視野拡張トレーニング
① ストロボドリブル(Stroboscopic Dribbling)
概要
ストロボグラス(視覚を瞬間的に遮断する特殊メガネ)を装着した状態で行うドリブル練習です。
目的
視覚情報が制限された状況でのドリブルを通じて、ボールを保持しながら周辺の情報を素早く処理・判断する能力を高めます。
- 選手はストロボグラスを装着し、視覚情報が断続的に途切れる状態でドリブルをします。
- ドリブル中に、コーチが出す指示(ターゲットや方向の指定など)に素早く反応します。
- 視覚情報が制限されているため、周辺視野の活用と、視覚情報が途切れた瞬間を予測する能力が鍛えられます。
- 慣れてきたらドリブルの難易度や指示の頻度を上げるとさらに効果的です。
② 周辺視野反応ドリル(Peripheral Vision Reaction Drill)
概要
周辺に配置されたターゲットに対し、迅速かつ正確に反応するトレーニングです。
目的
周辺視野の認識力を高め、視界の広がりを最大限活用して複数の情報を同時に処理する能力を向上させます。
- 選手は中央を向き、周囲に配置された複数のターゲット(光や色、数字など)を周辺視野で捉えます。
- ターゲットがランダムに提示されると、素早くその方向に反応(タッチ、ポイント、方向指示)します。
- 正面を見たまま、いかに正確に周辺視野の情報を拾えるかが重要になります。
- ターゲットの距離や速度、提示方法を変化させることで難易度調整が可能です。


③ デュアルタスクパス(Dual Task Passing)
概要
認知的な課題(数字や色の識別など)を行いながら同時にパスを繰り返すトレーニングです。
目的
認知負荷(脳が行う作業)を高めた状態で、視野を広く保ち、複数のことを同時にこなす能力(マルチタスク)を向上させます。
- 選手はパートナーとパスをしながら、別の課題(例えば提示された数字や色を声に出して言う、コーチのジェスチャーに応答するなど)を行います。
- これにより視野を広げつつ、意識を複数のタスクに分散させる能力を養います。
- 慣れてきたらパスの速度を上げたり、課題の難易度を高めることで、より高度な視野拡張と認知能力向上が期待できます。
視覚反応速度短縮トレーニング
① スキャンビジョン(Scan Vision)
概要
競技中に必要な「素早い周囲確認(スキャニング)」の速度と精度を高めるトレーニングです。
目的
周囲の状況を一瞬で把握し、的確な判断につなげる能力(視覚的反応速度)の向上を目指します。
- 選手は中心の目標(ボールや選手)に焦点を合わせつつ、左右や背後など周囲の情報(数字・カラー・コーンなど)を高速で確認します。
- コーチがランダムに提示する情報に即座に反応する必要があります。
- 最初はゆっくり行い、徐々に視覚確認のスピードを速めていきます。
サッカーなどで「スキャン動作」を習慣化し、試合中に瞬間的な情報処理能力を高めるために有効です。
② ストロボキャッチ(Stroboscopic Catch)
概要
ストロボグラスを用いて視覚情報が制限された環境下でボールをキャッチするトレーニングです。
目的
視覚が断続的に制限された状態で動作を行うことで、脳が短い情報提示から瞬時に反応する能力を向上させます。
- 選手はストロボグラスを装着し、パートナーが投げるボールをキャッチします。
- ストロボグラスは断続的に視界を遮断するため、視覚情報が限られる中でボールの位置を素早く認識して反応する必要があります。
- 慣れてきたらボールの速度や方向をランダムに変えて難易度を高め、反応速度をさらに鍛えます。
ハンドリングやキャッチングが重要な競技(ラグビー、アメフトなど)で非常に効果的です。
③ Okkuloライトトレーニング(Okkulo Light Training)
概要
特殊な照明(Okkulo)を用いて、通常よりも暗く調整された環境で動作を行うトレーニングです。
目的
暗い環境下で視覚情報の処理を素早く行えるようにすることで、通常の明るさに戻った時に劇的に反応速度を高める効果があります。
- Okkuloシステム(照明を低く抑えた特殊なトレーニング環境)を用いて、暗所でボールキャッチやシュートなどを行います。
- 目が視覚情報を捉えるために通常より速い反応を求められるため、視覚処理速度が自然と高まります。
- 慣れてきたら動作速度を高めたり、照度をさらに下げてチャレンジングな環境を作ります。
サッカー、野球、ホッケーなど動体認識の速さが求められるスポーツで非常に有効です。
Okkuloシステムはアメリカやヨーロッパでは一定の認知度がありますが、日本ではまだほとんど導入例がなく、あくまでも紹介レベルとしての位置づけです。
これらのトレーニングを導入することで、視覚反応速度を短縮し、「素早く正確に反応できる選手」へと進化することが可能です!
参考文献
📄 論文①
タイトル:「Training vision in athletes to improve sports performance」
出典:Frontiers in Sports and Active Living(2024)
✅ 要点まとめ
•視覚トレーニングは「実戦に近い形式(Naturalistic Training)」が最も効果的
•基礎スキル訓練(Component Skill)は効果が限定的
•統合型訓練(Integrated Batteries)は研究結果にばらつきあり
•高品質なエビデンスの蓄積が今後の課題
📄 論文②
出典:Frontiers in Sports and Active Living(2020)
✅ 要点まとめ
•大学野球選手にDVTを実施 → バッティング練習の精度(飛距離・角度)が向上
•視覚機能全般や試合成績には有意差なし
• 技術習得への影響はあるが、実戦パフォーマンスには直結しなかった
📄 論文③
タイトル:「Enhancing Tennis Performance through Visual Training: The Efficacy of Dynamic Vision Exercises」
出典:Journal of Human Sport and Exercise(2023)
✅ 要点まとめ
•テニス選手に対し、8週間の視覚トレーニングを実施
•競技力(ITNスコア)・動体視覚・反応時間が大きく改善
•静的視力の改善はわずかで、判断・反応の視覚機能に特に効果大
📄 論文④
出典:Frontiers in Human Neuroscience(2024)
✅ 要点まとめ
•エリートスキート射撃選手にSVTを6週間実施
•視覚運動スキル・射撃精度・反応時間すべてで有意な改善
•動作の安定性(銃のブレやピーク速度)も向上
• SVTは“見る→判断→動作”の一連プロセスの質を高める
📄 論文⑤
タイトル:「The effect of stroboscopic vision training on the performance of elite curling athletes」
出典:Frontiers in Human Neuroscience(2023)
✅ 要点まとめ
•SVT(視覚処理・スピード制御)、TFT(配石精度)にそれぞれ特化した効果
•両方とも時間・速度認識において有意な改善
• 両者の併用が最も効果的
📄 論文⑥
タイトル:「New perspectives on the role of vision in sports」
出典:Frontiers in Human Neuroscience(2023, Editorial)
✅ 要点まとめ
•スポーツにおける視覚の役割を再定義
•ストロボ、VR、固視訓練などの制限環境が適応力を高める
•視覚は「第3のトレーニング軸」として位置づけられるべき
📄 論文⑦
タイトル:「Light-based manipulation of visual processing speed… in professional soccer players」
出典:Ophthalmic and Physiological Optics(2024)
✅ 要点まとめ
•Okkulo照明による暗所視覚トレで
→ 動体視力 +8.4%、反応時間 -30%超
•周辺視・識別力も大幅向上
• 視覚に“負荷”をかけることで処理スピードを改善
📄 論文⑧
出典:Clinical and Experimental Optometry(2024)
✅ 要点まとめ
•動体視力(DVA)は、静止視力・乱視・立体視と中程度の相関
•両眼視力との相関はなし
• 乱視や深視力の矯正がパフォーマンス向上に重要
📄 論文⑨
出典:Frontiers in Human Neuroscience(2024)
✅ 要点まとめ
• SVT(6週間)で視覚運動スキルが有意に向上
•命中精度 +5.83%、反応時間短縮、銃操作のブレ低下
•「見る→判断→動作」の効率を高める
📄 論文⑩
•タイトル: 「Role of Sport Vision in Performance: Systematic Review」
•出典:Buscemi et al.(2024)
✅ 要点まとめ
1. 競技ごとに視覚スキルは異なる ─ バスケ・サッカー=動的立体視、ゴルフ・射撃=静的立体視+バランス制御
2. 視覚トレーニングは運動機能とも深く関連 ─ 動体視力・周辺視野・認知スキルが向上、ケガ予防や姿勢制御にも貢献
3. 徒手療法(OMT)による補助の可能性 ─ 頭蓋の歪みや乱視の調整が視覚スキルに好影響を与える報告も
4. 評価基準の標準化が今後の課題 ─ PSVPPなど評価ツールはあるが、測定法の統一が不足
📄 論文⑪
•タイトル: 「Stroboscopic visual training: The potential for clinical application in neurological populations」
出典:Das et al.
✅ 要点まとめ
1. SVTは健常者に即時効果あり ─ 5〜7分の実施でも注意力・反応時間・短期記憶が改善
2. 神経疾患への応用は可能性ありだが研究不足 ─ 多発性硬化症での事例は1件のみ、安全性や効果の検証が必要
3. 高齢者や疾患対象では刺激が強すぎる懸念も ─ 慎重な導入設計が必要
4. 今後は標準化と安全性評価が鍵 ─ 統一プロトコル・使用時間・適応条件の整備が重要
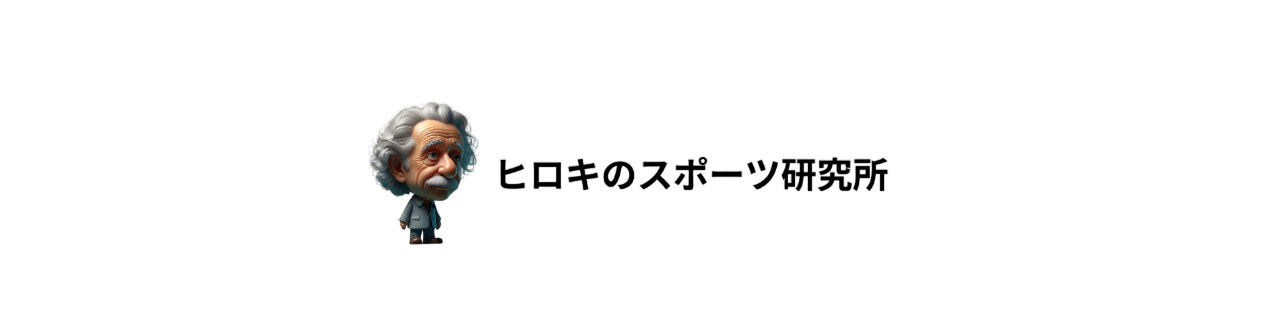



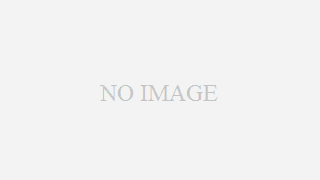





コメント